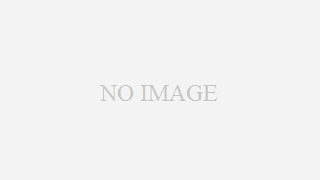 社会
社会 【日本の歪みまくった資本主義】権利は譲らない、給料を払いたくない、だけど…
権利は譲らないが、労働力は欲しい 日本企業での外国人労働者に対する姿勢はかなり頭がおかしい。 農業や漁業、酪農の人手不足に対応するために多くの外国人労働者を受け入れている。 だが、外国人労働者が独立することはほとんどない。 農地を与えはする...
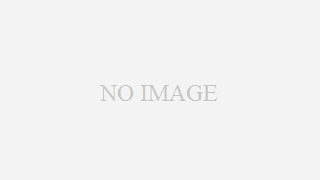 社会
社会 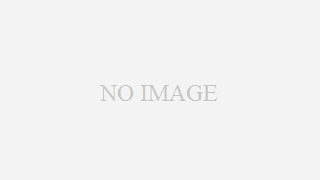 ライフハック
ライフハック 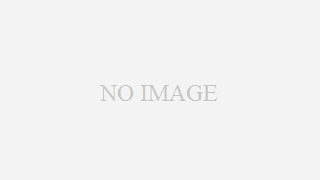 社会
社会 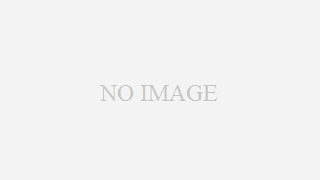 社会
社会 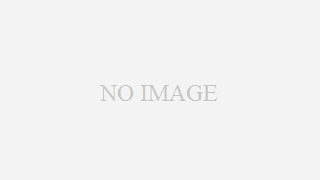 社会
社会 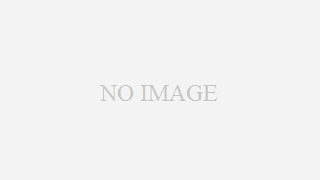 社会
社会